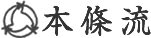本條秀咲(家元:本條秀太郎)が
熊本県菊池市旭志を中心に、
小学生からシニアまで幅広く
三味線を教えています。
講師紹介

はじめまして。本條秀咲(ほんじょうひでさき)と申します。
山鹿市鹿央町生まれの午年です。
祖父母の影響で、時代劇が好きになり、大学では古文書解読に励みました。
タイに短期留学した際、日本のことを聞かれても、何も答えられない自分に愕然としました。
就職活動もしないで実家に戻り、たまたま山鹿灯籠踊り保存会の事務局の臨時職員となり、踊り手として、保存会に入会しました。
その活動の中で、山鹿温泉祭で三味線を弾きながら練り歩く人を募集され、「ちょっとやってみようかな」と思ったのが、この道に入るきっかけです。その時、保存会の地方(唄、三味線、笛、鳴り物)の指導をされていた師匠(本條秀美先生)と巡り合い、20年が経とうとしています。
教室では、「最初が肝心」、三味線の取り扱い、姿勢、バチの持ち方など、基本的なことを大事に教えています。譜面の読み方を覚えたら、知らない曲でも弾けるようになるのが目標です。
発表会などでは、着物を着て演奏します。着物を着る、また、着付けの勉強にもなる、いい機会です。みんなで合奏すると、達成感があります。
みなさん、ぜひ、日本の伝統文化である三味線を始めてみませんか。
参考:本條流ホームページ(東京)
師匠・本條秀美先生のご紹介
本條秀咲の師匠である本條秀美先生は、NHK大河ドラマ「徳川慶喜」や「元禄繚乱」にて演奏するなど多数の実績がございます。
熊本市で教室を開いておられ、発表会や文化祭などへ参加させていただいています。
詳しくは先生のホームページをご覧ください。

本條流について
本條流とは俚奏楽を流儀曲としています。
俚奏楽の普及・発展のために古典音楽としての「端唄」を始めとし、民俗歌謡曲としての「民謡」、そして伝統的現代的三味線の奏法などを学びます。
三味線音楽を学び、人々との交流を通じて心の豊かさを高めていくことができます。